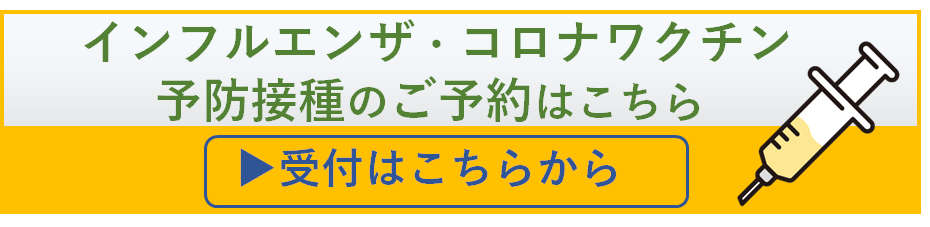クリニック案内

○各種健康保険取扱い
○駐車場あり(12台完備)
○原則院内処方
| 医院名 |
|---|
| 内科萱場クリニック |
| 院長 |
| 萱場 佳郎 |
| 住所 |
| 〒983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原1-5-32 |
| 診療時間 |
| 8:30~12:00、14:30~18:00 ※土曜日は9:00~12:30までの診療 水曜、土曜午後、日曜、祝日休診 |
| 電話番号 |
| 022-256-5101 |
| 連携病院 |
|
ご予約・ご相談
「どんな治療法があるの?」
「治療にかかる期間は?」
疑問に思う事、何でもご相談ください。お電話より承っております。
TEL 022-256-5101
トピック
鼻炎の季節
立春が過ぎて、今年もスギ花粉による鼻炎の季節がやってきました。
鼻炎は、大きく3つ、
① アレルギー性:スギによる季節性や、ハウスダストによる通年性などの鼻炎
② 感染性:ウイルス、細菌などの感染による鼻炎
③ 非アレルギー性:寒さで鼻水がでる血管運動性や、点鼻薬の使い過ぎでの鼻炎など
に分けられています。そのうちアレルギー性鼻炎の有病率は約50%とされ、この20年でスギ花粉症は約22ポイント増加しています。また小学生の新規の発症は、新型コロナ感染の流行前と比べると、新型コロナで皆がマスクをするようになったら、半分以下に減ったとの調査があります。
今年仙台では、例年と比べて多量に飛散するとされています。花粉症の予防は、まずは体に花粉を近づけない、家に入れないことであり、帰宅時は髪や上着から花粉を払い落してから、部屋に入りましょう。また花粉情報から飛散が多い時は外出を避ける、眼鏡やマスクをして外出する、窓を開放しない、洗濯物を外に干さないようにして、もし家に取り込む時は、花粉を落としてから入れるようにしましょう。
症状を抑えるためには、まず抗ヒスタミン薬の内服となります。多くの種類の薬が出ていますが、脳内に移行する比率が高いものから低いものまで様々です。比率が高い薬は、眠くなる、作業効率が落ちるとされ、自分では気づかないまでもミスが増えるとされています。そのため添付文書では、「自動車運転、危険作業は行わないこと」、「注意すること」と記載されているものがあり、高齢の方では、転倒・骨折等の事故につながることがあります。また市販の総合感冒薬にも、同じように鼻水を抑えるために、抗ヒスタミン成分が入っていますが、多くは脳内に移行する比率が高い成分が入っています。そのために眠くならないようにカフェイン等の興奮作用のあるものも併せて入っています。
以前から飲んでいて大丈夫と思っていても、まずは確認してから内服するようにしましょう。
いろいろな部位で
新年となって、大寒、立春を過ぎても寒さはますます本格的になります。暖房をつけて、厚着をして防寒をしていきますが、寒いと体表面の血管は熱が奪われないように収縮します。そのため血圧は上がり、心臓に負荷がかかって、心臓の血管(冠動脈)は血液の供給を増やそうとします。しかし動脈硬化が進んでいると、血液量の供給を増やせずに、心筋が酸素不足に陥って、痛み(狭心症)として現れます。実際には、胸が締め付けられる(絞扼感)、押し付けられて苦しい(圧迫感)、焼けるようだ(灼熱感)などと表現されます。痛みの部位は、左前胸部、左肩、みぞおち、首すじ、歯ぐきに拡がるなど様々です。
原因には冠動脈の動脈硬化(狭窄)があり、それをおこす危険因子には前もって注意が必要です。この危険因子は普段から健康診断で行われる項目であり、まずは喫煙、LDLコレステロール高値、糖尿病、高血圧、肥満、高尿酸血症、年齢となります。年齢は誰にも避けられませんが、他の因子は減らすことが可能です。早いうちに、対応していきましょう。
狭心症のタイプとしては、
① 極端にストレス、緊張、興奮したり、階段を上ったり、息を切らすくらい体を動かした(労作)時に胸が苦しくなり、休めばまもなく直るというもの
② 就寝中、特に明け方に胸が苦しく押さえつけられたようになって眼を覚ましてしまう
などがあります。このような症状の回数が増え、さらに長い時間続くようになってくると注意が必要です。そのまま症状を繰り返している間に、いつのまにか心筋梗塞になってしまう場合もあります。
日本人の死亡原因、特に年代別高齢者の1,2位は(心筋梗塞も含む)心疾患です。
心筋梗塞が発症した場合の治療は、脳卒中と同じように時間との勝負になります。心筋がダメージを受ける前に治療を受ければ、日常生活への復帰も早くなります。
病院受診、治療が遅れる理由としては、この痛みはまもなく治まるはず、急いでいくのは大げさで恥ずかしい、前にかかった五十肩や胃潰瘍などの他の病気に違いない、自分は心筋梗塞になるはずがない、といった思いがあげられています。軽い症状が頻回に起こっているようであれば、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。ただ、いつもと違う強く、長い症状がでたら、迷わずに救急で医療機関を受診しましょう。
飲み込みが
年の初めには餅を食べる機会が増えますが、それと共に喉に詰まらせての痛ましい事故が毎年報道されています。
餅に限らず、ものを食べたり飲んだりしたものが気管に入ってしまう誤嚥が、加齢と共にみられてきます。飲み込みに関わる筋肉や感覚がしだいに衰えるためであり、40歳台から始まるとされ、特に高齢の方や脳梗塞、パーキンソン病などの神経の病気、認知症などで多くみられています。普通は気管に入ってしまうと、むせる、せき込む等の症状がでます。しかし嚥下(飲みこむ)反射の低下、のどの筋力の低下、咳反射の低下がおこると、咳などが出ずに、気づかないまま重篤な肺炎(誤嚥性肺炎)になりかねません。通常、肺炎ではひどい咳、発熱、膿性の痰が多くでますが、なんとなく元気がない、食欲がない、のどがゴロゴロしている、呼吸が浅くて早いなど、症状としてははっきりしないのが誤嚥性肺炎と特徴をされます。そのため家族や周囲の方の観察、気づき方が重要となります。
誤嚥を防ぐ食事としては、会話をしながら食べる、背筋を伸ばして、良い姿勢で食べる、噛み応えのある食事をする、よく噛んで早食いはしない、食後にすぐに横にならない、七味、唐辛子やミントなど香辛料、ハーブで喉を刺激する、体温と温度差のある(温かい、冷たい)食べ物をとっていきましょう。嚥下力を鍛えるトレーニングでは、①臍をのぞくようにあごをひきながら、額を手で押して、喉ぼとけに力をいれる、②あごを引きながら、あごの下に親指を当ててあごを押し上げて押し合うようにして、喉ぼとけに力をいれていきます。ただ、やり過ぎると首を痛めるので、注意してやっていきましょう。
誤嚥性肺炎の原因となる菌は、口腔内の常在菌(虫歯菌)や肺炎球菌であり、菌が増殖しないように日ごろから口腔内を清潔に保つ、食べかすが残っていないようにしましょう。肺炎球菌に対しては、65歳以上の方で定期の予防接種が既に始まっています。100種類ほどある肺炎球菌株に対して、以前よりも広くカバーできる予防接種薬も出てきました。以前接種した方も含めて、気になる方は医療機関で相談してみましょう。
食後の痛み
これから年末年始にかけて、会合などで夜遅くまで飲食の進む時期になります。そしてその楽しい食事の後、深夜になって右の肋骨付近が急に痛んで、眼を覚ますことがあります。原因として多くは胆石によるもので、胆石の約4分の3は、胆のう内にできます。胆のうは、洋ナシを逆さにしたような形をしており、普段肝臓から出る胆汁を貯めていて、食後にその胆汁を管(総胆管)を通して腸に流すために収縮していきます。その「洋ナシ」のヘタ付近(頚部)に石が挟まってしまうと、激しい痛みをおこしてきます。またその石が総胆管につまって感染をおこすと、激しい痛みや発熱をおこして命に関わる事態もあり得ます。
胆石には、コレステロールからできるコレステロール石や、細菌が原因でできるビリルビンカルシウム石などの色素石がみられます。胆石は、健診やドックの超音波検査で指摘されることがありますが、見つかっても通常は経過観察とされます。ただ食後の痛みが頻回に起こる場合や、あまりにも石が多くて胆嚢の壁が観察できない状態や慢性的に胆のうの壁が炎症をおこしている時、胆のうの収縮能が低下してしまった時は、治療の対象とされています。
症状としては、急な右の肋骨付近の痛みの他に、吐き気、嘔吐、右肩や肩甲骨への痛みがおこることがあります。胆石発生のリスクとしては、肥満、カロリー・動物性脂肪の摂りすぎ、中性脂肪高値、急な体重減少、ダイエット、長期間の経口避妊薬使用などがあげられています。肥満の方の25%には胆石があるとされ、成人の肥満は、特に男性では人口の1/3程度に増えており、胆石の方は増えていると考えられています。リスクを減らすとして期待できるのは、野菜、大豆などの植物性蛋白、魚油、ナッツ、ダイエット中での脂肪摂取、ジョキング、自転車などの運動などが挙げられています。
まずは、ドックや健診ででも腹部の超音波検査を受けていきましょう。胆のうの壁の一部が厚くなったりすることがあります。それは悪性との鑑別が必要なこともあり、何かを指摘されたことは、定期的に検査を受けていくか、ぜひかかりつけ医に相談してみましょう。
飛び出して
食物が、食道、胃、小腸、大腸といった管を通っていくとき、内視鏡検査で管の内側からみると落とし穴のようにくぼんで見える箇所(憩室)ができていることがあります。特に壁の薄い大腸には多発しやすく(大腸憩室)、右の脇腹下腹部(上行結腸、盲腸)と左下腹部(下行、S状結腸)に多くみられます。日本人の2~3割にはみられるとされ、内視鏡検査やCT,バリウム検査でみつかります。普通、消化管は収縮したり緩んだり(弛緩)を繰り返して内容物を下流に送る時に、精神的、肉体的ストレス等でその動き(蠕動運動)が乱れることがあります。また便秘、食物繊維不7足で便の体積が減ってしまい、そこに腸の収縮緊張した状態が続いて、内容物の圧力によって壁が飛び出してしまったのが憩室です。そのため、できてしまった憩室はその後治ることはありません。大腸では、普段憩室に大便が入っており、そこで細菌が増殖すると、局所的に炎症をおこすことがあります(憩室炎)。さらに炎症が進行すると周囲に膿瘍を作ったり、出血したり、穿孔を起こすなどの重い合併症を起こすことがあります。
大腸憩室炎の症状として、急に強い痛みとして起こることがあり、また痛みは強くないものの、突然下血したり、発熱することもあります。症状が持続するときは、重い合併症をおこす前に早めに医療機関を受診しましょう。憩室炎には再発もみられます。年に何回も入院するような状況の場合は、社会生活が困難として、原因となる部位を手術で切除してしまうこともありえます。憩室は、一般に加齢と共に増えていきますが、予防としては、肥満、運動不足を避けること、禁煙、運動を心がけて便秘を避けていきましょう。また憩室がすでにあるとわかっている時は、バリウムがはまり込んでしまうため、胃のレントゲン検査は避けることが必要です。
秋からの予防接種
10月からは、今年もインフルエンザの予防接種が始まるとともに、再び新型コロナワクチンの定期接種が始まります。定期接種の対象は、昨年同様65歳以上の方となります。今年の夏からは、すでに新型コロナ感染が増加傾向にありました。以前からのオミクロン株からの変異株で、NB1.8.1(通称ニンバス)とされています。今年は酷暑の中で、のどの痛みや鼻水、咳などいわゆる夏風邪症状の方がみられていましたが、そこに発熱が加わると、新型コロナ感染が疑われて、抗原検査でも陽性が多くみられていました。ニンバスは上気道(鼻、のど)に、少しのウイルスでも感染をおこすことから、以前の下気道(肺付近)で感染する従来の株よりも、感染が拡がりやすいとされています。暑いためにマスクは敬遠され、密閉した冷房の効いた部屋で、外への換気を減らしてしまい、お盆などで大人数が集まるところに行くという、以前の密閉・密集・密接=3密がおこりやすくなりました。症状の特徴は、なにかが刺さったような、非常に強い喉の痛みです。ただ必ずその症状が伴うわけではないことから、発熱を伴った風邪症状では、新型コロナ感染はまず疑っていきましょう。定期接種の対象となる65歳以上の方には、今年は公的助成がついた上で自己負担額が8000円となります。昨年は3500円だったことから、助成額が減らされてきました。自己負担は増えますが、特に高齢の方や糖尿病など、免疫力が低下して重症化へのリスクが高い方は、ぜひ予防接種を検討していきましょう。
また今年度に65歳になる方は、肺炎球菌ワクチンへの公的助成が受けられます。65歳今年度限りの助成であり、来春までの残り半年です。さらに今年春から公的助成対象となった帯状疱疹ワクチンは、65歳、70歳、75歳と、5歳刻みでの対象となり、その年齢の方も残り半年です。希望される方は、早めに対応していきましょう。
秋には
立秋が過ぎてもまだまだ暑いですが、日の入りが徐々に早くなって、秋の訪れを感じるようになってきました。秋には夜長を楽しみたいもので、リラックスして眠りにつきますが、高齢の方の3割は、睡眠に悩まされているとされています。不眠のタイプとしては,3つのタイプがあるとされ、
①
中途覚醒:就寝中に目が覚めてしまい、トイレに頻回に行くなど、最も多い型
②
入眠障害:床にはいっても寝付けない、考え事をしまって眼が冴えてしまう型
③
早朝覚醒:起きようとする予定時間の2時間以上前に覚めてしまう型。そのため極端に早く床に入って早寝早起きとなり、家族との時間がずれてしまう。
が、挙げられています。ヒトには体内時計があるとされ、その体内時計で朝に目が覚めて、夜は眠くなるとされています。その体内時計の働きが、高齢の方は弱くなってきたために、中途覚醒がおこりやすくなるとされています。その体内時計の一日は、24時間よりいくらか長いとされ、そのままだと時間がずれて行ってしまいます。そのため太陽光など強い光が目に入ることで、24時間にリセットされて、脳が覚醒するとされています。そのため朝早くに太陽光を見ると、だんだんと早朝覚醒に傾くとされており、対策としては、早い時間に目覚めてもカーテンで遮光して、光を浴びないようにしましょう。また逆に夕方、夜に強い光、テレビや液晶の強いブルーライト等をみると頭が覚醒して、入眠障害になりかねません。就寝前は光量を落としておきましょう。
また睡眠には疲労回復効果もあり、日中の運動量、疲労度によって睡眠時間、深さが影響するとされています。日中から夕方にかけて軽く汗をかく程度の有酸素運動をすることで、入眠障害の改善効果が期待されます。その方の体力や体調に応じてやっていきましょう。また入浴も体調をリラックスさせる効果があり、40度のぬるめの湯温で10~15分の入浴で脳や内臓の温度をあげていきます。また浴室から出て、すぐに寝るのではなく、2時間ほどあけてから布団に入ることで、脳もリラックスして眠りに入りやすいとされています。不眠対策のコツとしては、「眠くなるまで床に入らない」、「睡眠にメリハリをつける」、早朝覚醒では「朝日を避ける」ことがあります。就寝前にコーヒーなどカフェインの入った飲み物、パソコンやテレビに見入るのは避けましょう。
また、夕方から夜にかけて足が熱い、痛い、痒い、虫がはっているようだ、むずむずしてきて、そのために寝付けないといった「むずむず足症候群」が知られています。人口の2~4%の方にあるとされており、年代が関係なく発症していることから、もしそういった症状があれば、かかりつけ医に相談してみましょう。
暑くて
今年は梅雨入りと発表されてもなかなか長雨にはならず、夏日など暑い日が続いています。そして熱中症警戒アラートは、毎日各地で出されるようになっています。
熱中症は、体温をコントロールしている脳は平熱に設定しているのに、体温が異常に上昇して汗などの冷却がうまくいかない、異常状態に陥った状況です。熱中症を引き起こす要件は、環境、体調、動きにかかってきます。
「環境」高温や湿度が高い、風がない、直射日光が当たる炎天下、発熱を伴った調理場や、エアコンを使っていない閉め切った部屋の中
「体調」風邪や下痢での脱水、糖尿病、二日酔いなど
「動き」長時間の激しい筋肉労働や、激しい動きのスポーツ、運動による発熱
等が重なって引き起こされていきます。それぞれのリスクに注意しての予防が重要です。
熱中症による救急搬送は、統計では高齢者が最も多く、次いで成人、少年、乳幼児の順になっています。また発生場所としては、家の中が最も多く、ついで路上や屋外等となっています。屋内での高齢の方の場合は、暑さを感じにくく、のどの渇きに気づかずに徐々に脱水状態に陥って、重症例が多いとされています。家族の方は、室温に注意して脱水予防に飲水を声がけしていきましょう。炎天下など、発汗が多い状態での水分補給では、真水や麦茶等の水分だけではなく、塩分も補給していきます。また逆に塩飴など塩分だけなめるのではなく、経口補水液やスポーツドリンクを利用して、水分も十分にとっていきましょう。
熱中症をおこしやすい職場では、今年6月から法律で熱中症の疑いのある労働者を早期に発見(体制整備)して、緊急連絡網や搬送先など速やかに対処するための「手順作成」し、それを作業者全員に周知徹底(関係者への周知)が義務付けられました。
また昨年からは、外出先での熱中症予防のために, 自治体が冷房設備のある指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しています。仙台市でも、市民センター等の仙台市施設、スーパーなどの商業施設、薬局等と提携して指定しています。 せんだいクーリングシェルターのポスター掲示があることから、利用してぜひ熱中症を予防していきましょう。
雨の日に
今年も梅雨のじめじめとした季節になります。毎日が雨では気分も落ちこみますが、体調も不調になったりすることが知られています。
雨の日や、夕立の前に肩こりや頭痛、めまい等の症状がおこる方がいます。また以前からあった腰痛や、膝や肩の痛みが悪化することがあり、これらの天候の変化に伴う不調は、気圧や湿気の変化が原因として、いわゆる「気象病(天気痛)」と言われています。ただ、これは健康保険上の正式な病名ではなく、気象の変化でおこる不調の総称とされます。
気象病で起こる症状としては、頭痛がもっとも多くみられ、まただるさや肩こり、めまい、耳鳴り、関節痛、動悸など多岐にわたるとされています。これまで、原因としてすべては明らかにはなっていませんが、第一には脳に情報を伝える耳の鼓膜の奥にある内耳の不調が原因とされています。内耳が気圧の変化を感知して、脳への情報伝達が過剰に反応することで自律神経が乱されて、頭痛やめまいといった症状がおこるものと考えられています。自律神経には交感神経と副交感神経があり、通常はそのバランスによって体調が保たれています。日ごろ、交感神経は日中の活動時に優位となり、血圧や脈の上昇、発汗、内臓の動き等に影響します。一方副交感神経は、就寝中に優位となり、体を休める方向に働きます。そのため交感神経が異常に優位になるとめまいや頭痛などがおこり、副交感神経が優位になると、だるさや気分の落ち込みが出てしまいます。
治療としては、根本原因としての気圧や湿度の加減は無理なことから、まずはそれぞれの症状に対する対症療法になります。頭痛や関節痛については痛み止め、めまいでは市販薬では車酔いの薬、全身では漢方薬等とさまざまな薬が使われます。ただ、強い頭痛やめまいがおこったら、重篤な病気が潜んでいることがあります。症状が重い時には、かかりつけ医や神経内科医にぜひ相談してみましょう。
健診の項目
今年も6月から特定健診、7月からは基礎健診が始まります。これらの健診では、会社の健診にはない「尿酸」の項目があります。尿酸値が高くなると、痛風発作へのリスクが上がるほかに、動脈硬化を進めていくことから、メタボ健診である住民健診には、「尿酸」が含まれています。高尿酸血症が続くと、痛風発作のほかに、将来の心筋梗塞や脳卒中、尿を作る能力(腎機能)が低下する慢性腎臓病、ひいては人工透析導入につながりかねません。痛風発作は男性に多いとされ、関節内に尿酸の結晶が析出することによる関節炎であり、足に起これば、痛みや腫れで歩行も不自由となります。また尿酸が尿に排出されて沈殿すれば尿管結石の原因となって、激しい痛みを引き起こすことになります。
尿酸値のコントロールは6-7-8とされます。尿酸の基準値上限は7㎎/dlであり、9㎎/dl以上や、8㎎/dl以上でも合併症(腎障害・高血圧・糖尿病・肥満など)がある場合は、治療の対象となり、尿酸値6㎎/dl以下を維持することが望ましいとされています。
尿酸の原因として、まずはプリン体の摂りすぎとされ、食品では干物類(魚やスルメ、ビーフジャーキー等)、レバー等の内臓類に多いとされています。また飲酒ではプリン体フリーをうたったアルコール飲料が出ています。ただアルコールが分解される時には、肝臓でプリン体ができてしまい、プリン体フリーのビールでも、他の焼酎や日本酒、ウイスキーでも結局尿酸値上昇の要因となります。適量のアルコールを守っていきましょう。
その他の原因としては、第一に太りすぎ、②果物や清涼飲料水に含まれる甘味成分(果糖)の摂りすぎ、③息を止めて行う腕立て伏せなどの無酸素運動が挙げられます。果糖は肝臓で分解する時に尿酸ができてしまい、砂糖も、果糖とブドウ糖からできていることから注意が必要です。運動は、ジョキングなど軽く汗ばむような有酸素運動を続けていきましょう。
これらからメタボ予防のために、住民健診やドックでは尿酸値項目が含まれています。高尿酸血症への対応としては、治療や生活習慣の見直しが必要となることから、気になる方はかかりつけ医に相談してみましょう。
けんしんの目的
新年度となり、今年も住民健診や職場の健康診断が始まります。仙台市の特定健診では従来通りに年内は6~9月、75歳以上の方、35~39歳の方の基礎健診は7~9月に行われます。
「健診」は、健康であるかを確認するとともに、病気になる危険因子を探すのが目的であり、危険因子が見つかった時には、生活習慣を改めて健康管理をしていくことになります。健診の中で法律で決まっているものには、先ほどの特定健診や、職場の定期健康診断、また学校健診が挙げられます。特定健診はいわゆるメタボ健診であって、将来の動脈硬化を抑えて心筋梗塞、脳卒中発症のリスク、人工透析に至らないように予防していくというものです。また会社の定期健診は、労働者が健康で業務につけるように雇用者が体調を把握することが目的です。そのためこれらの健診の結果をみるだけで、病気の危険因子に対して何ら対策をしなければ、健診の目的からは、ずれてしまうことになります。
一方、特定の病気を早期に発見して治療することを目的とした「検診」もあります。大腸がん、胃がん、肺がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん等の検診がこれにあたり、国や自治体が検診事業を行うための費用と、検診でがんが発見できる割合から、費用対効果として、より効果的な方法で行われます。大腸がん検診では、40歳以上で便潜血検査、胃がん検診では40歳以上では胃部X線検査を毎年、50歳以上では胃部X線検査を毎年、もしくは内視鏡検査を2年に1回、肺がんは40歳以上で胸部X線検査の受診、などを勧めています。
今年の仙台市の健診の申し込みは、従来通り4月の市政だよりのはがきでの申し込みと、インターネットで、「仙台市 市民健診」での検索からの申し込みも可能となっています。申し込み項目に迷う時は、かかりつけ医に相談の上でぜひけんしんを受けていきましょう。
春からの予防接種
数日前から胸や腹、顔や頭部に何か違和感があると思っていたら、赤く痛痒くなって、その後ひどい痛みとともに発疹、水疱に変わっていくことがあります。帯状疱疹として知られていますが、最近発症する方が増えています。また発症した方の7割程度は、50歳以上の方が占めており、80歳までに3人に1人は経験するとのデータもあります。小児期で感染した水痘・帯状疱疹ウイルスが、顔の三叉神経や脊椎の神経節細胞に残っていて、免疫能が落ちてきた50歳台以上で、ウイルスが再び活性化すると発症してきます。特に顔面の三叉神経では、文字通り三本に分かれていることから、目の近くの神経では、角膜炎や視力低下、耳から顎にかけてでは、顔がゆがむなどの顔面神経麻痺、難聴、脳に行けば脳炎発症のリスクが知られています。このウイルスは、治療で死滅させることはできませんが、予防接種をすることで、発症を抑えたり、後遺症リスクを減らすことが可能とされています。そして令和7年4月からは、公的助成の上で接種ができることになりました。
対象は65歳の方で、5年間の経過措置として65歳、70歳、75歳・・・と5歳ごとの方が対象として行われます。7年度65歳、70歳、75歳・・・になる方は7年度中に行い、また66歳、72歳などの方は、今後70歳や75歳になった時に公的助成でできることになります。なお公的助成の年齢を待たずに、希望時に全額自費で接種をすることも可能です。
ワクチンには2種類あり、子供も接種する従来の生ワクチンと、ウイルスの毒性を除いた不活化ワクチンがあります。仙台市ではそれぞれ費用のほぼ半額が助成されますが、生ワクチンは1回の接種で、5000円が自己負担となります。また不活化ワクチンは2ヶ月以上の間をあけて、2回の接種が必要であり、1回につき11000円の自己負担が必要となります。発症の予防効果は、一年後に生ワクチンで60%、不活化ワクチンで90%以上とされています。また後遺症として痛みが残ってしまう(神経障害性疼痛)ことへの発症抑制効果も、3年後で生ワクチンで60%、不活化ワクチンで90%以上とされていますから、費用と効果を考えて検討しましょう。またそれぞれに接種後の副反応も知られていますので、心配の時はかかりつけ医にまず相談してみましょう。
アレルギー
今年も立春が過ぎて、スギ花粉に悩まされる季節がやってきました。今年宮城県でのスギ花粉は、2月下旬から飛散し、終了は桜が散る頃、せいぜい4月いっぱいと予想されています。量は平年並みとされており、昨年よりは多くなるとの見込みです。毎年症状の出る方は、早めに内服を始めるなどの対策をとっていきましょう。
これはスギ花粉という異物の、鼻や口、皮膚に対するアレルギー反応であり、同様に口や皮膚から入る反応には、薬剤や食物による反応が知られています。
薬剤アレルギーの多くは、内服してから数分から2時間以内に起こる即時型アレルギーがあります。顔や首筋が赤くなったり、痒くなる、唇やまぶたが腫れるといった症状がみられます。また重症では、呼吸困難など命にかかわる(アナフィラキシー)事態に及ぶことがあります。内服初回から激しい症状が出ることもありますが、最初は軽く済んでいても、2回目になって激しく出ることがあります。特に解熱鎮痛剤は多いとされていますので、初めて飲む薬では、注意が必要ですし、内服して何かの症状がみられたら、2回目は飲まないようにするか、どうしても飲むときは特に注意していきましょう。
また内服の当初には問題がないものの、2週間以上経過してから症状がでることがあります(薬剤性過敏症症候群)。症状としては、発熱や発疹、肝機能障害等が現れることがあり、急に症状がでてきたら、まず内服中の薬をやめましょう。その上で処方した医療機関や薬局に相談するか、市販薬内服後の発疹では、その成分が記載された箱や書類を持って皮膚科などの医療機関を早めに受診しましょう。
入浴で
年が明けると、寒さはいよいよ厳しくなり、立春から春分へと春が待ち遠しくなります。また寒い夜には入浴で温まってから、就寝するのが楽しみです。
ただ入浴中の事故は冬に多いとされ、国の統計(令和3年)では、高齢者の浴槽内での不慮の溺死、溺水は4,750人と、交通事故での死亡数2150人の約2倍の多さとされています。そのため高齢の方は、特に注意が必要ですが、昨年12月には、有名な俳優・歌手の方も、50歳台で入浴中に亡くなっていたとのニュースがありました。
入浴の前後には血圧が大きく変動します。冬に暖房の効いた温かい部屋では、血圧はあまり変化していません。ましてや飲酒中には、血管が拡張して顔が赤くなるように、温かいと血管が拡張して血圧は下がっています。ただその後、部屋の外に出ると、寒さで血管は収縮して血圧は上がることになります。浴室は家の北側にあることが多く、脱衣室は寒くて血圧が急に上がります。その後お湯に入ると血管は広がって今度血圧は急激に下がります。そこで急に浴槽から立ち上がったりすると、脳が貧血状態となってくらくらしたり、意識を失って湯舟に顔をつけて溺れる事態となり、またその血圧の変動は、心臓に負担をかけていきます。特に高血圧や糖尿病、脂質異常、肥満、心臓病等の持病のある方、高齢の方は心臓に大きな負担がかかってきます。65歳以上の方は特に注意が必要です。
予防としては、
① 食後すぐの入浴、飲酒後アルコールが抜けていない状態での入浴は控える、高血圧のために内服中で、内服後の血圧の変動の大きい方は内服後の入浴は注意する。
② 居間だけではなくて、脱衣室も暖める、浴室も暖房をいれるか、もしくは給湯時に湯舟の蓋をあけておいて湯気を使って暖めておきましょう。
③ 入浴は41度以下のぬるめの湯に入り、湯舟につかるのは10分程度として、熱めの湯、長湯を避ける、高血圧や心臓病等のある方は肩まで湯に入らずに、胸付近でとどめる。浴槽から急に立ち上がらないようにします。
④ 入浴の際は家族に声をかける、周りの方も声を掛け合うようにします。
⑤ 万が一緊急事態を発見した場合は、まず浴槽の湯を抜く。浴槽から出せれば出して、人を呼ぶ、至急救急車の手配をしましょう。
これらに注意して、入浴中の不慮の事故を未然に防ぎ、快適に冬の入浴を楽しみたいものです。
かれて
寒くなってきて、いわゆる風邪やインフルエンザ、新型コロナ感染が再び増えてきました。その際には鼻水や咳、発熱と共に、のどが痛い、声がかれる(嗄声)症状がみられることがあります。
声は、気管への入り口にある膜状の声帯を閉じたり緩めたりしながら、息を吐くことで出しています。風邪症状と共にその声帯付近に炎症を起こしたり、痰がからむことでいつもの声が出なくなります。ただ、風邪症状がないのに声がかれたり、不調となることがあります。声帯の動きが不調となる原因として、①声帯の使い過ぎ、②声帯を動かす神経の不調、③異物、④刺激物によっての炎症、⑤老化などが挙げられます。
① 声帯の使い過ぎは、文字通り長時間、大声でのしゃべりすぎやカラオケの後などでみられます。そのため声を出さない、休めれば治っていきます。
② 神経の不調としては、脳梗塞の後遺症や、甲状腺や動脈瘤などによって声帯を動かす神経に不調をきたしたもので見られます。
③ 異物としては、声帯付近にポリープ、がんができて声帯の動きが制限されてしまうものです。
④ 刺激物での炎症は、タバコ成分のタールや飲酒によって声帯に炎症をおこした場合や、胃液が喉、声帯まで逆流して炎症をおこすものです。対応としては、喫煙や飲酒を控える、また逆流性食道炎の症状として、消化器薬が必要となります。
⑤ 加齢と共に声帯が委縮して、隙間から空気が漏れて声がかれます。
このような様々な原因で声枯れは起こりますが、声の使い過ぎなど、原因に思いあたることがあれば、声帯を休めて経過を見ていきましょう。ただポリープやがん、神経疾患では、放置していても症状の改善は見込めません。喉頭がんは、男性では罹患率が最も多い大腸がんの5%、女性では乳がんの0.5%程度ですが、ないわけではありません。進行すると手術で声を失うことにもなりかねません。声枯れの症状が続く時は、まず耳鼻科を受診しましょう。その上で声帯への神経による不調であれば、脳神経内科や呼吸器内科を、逆流性食道炎によるものであれば消化器内科に相談しましょう。
とどまる時間
年末年始には、会合で食べすぎ飲みすぎとなったり、夜遅くまでの飲食が多い時期になります。そうすると、寝る時や翌朝になっても胃が重くて、すっきりした空腹感を感じないことがあります。
噛み砕いた食物が胃に入ると、胃は動いて食物をこね始めて(収縮運動)、呑み込んだ唾液や胃酸、蛋白を分解する成分(分解酵素)と混ぜあわせます。そして、ご飯などの炭水化物や、肉等の蛋白質を、消化吸収しやすいようにドロドロ状態にしていきます。一方アルコールは胃の動きを弱めてしまう上に、こんにゃく、糸コン、海藻や野菜などの線維質、揚げ物等の脂肪分はなかなかどろどろ状態にはなりません。もともとこんにゃくや糸コンは、それを消化する分解酵素はヒトにはないために、そのまま腸に行って、大便のボリュームを作っていきます。油もの、脂質は、胃ではなく小腸に行ってから脂肪の分解酵素(リパーゼ)で消化が始まります。そのため鍋物や脂っこい食事では消化に手間取り、胃からなかなか排出されないために、胃のすっきりしない状態が続いていきます。量が多くないのに、食べて腹持ちのいい食べ物とは、胃からなかなか排出されない、消化に手間取るものとなります。
胃の中で食物のとどまる時間として、実際にはパンやお粥、半熟卵、リンゴ、バナナで2時間以内、白飯、そば、うどん、餅、芋等の炭水化物で2~3時間、肉や、ゆで卵、貝、エビ、焼き魚で3~4時間、脂身の入ったベーコン、揚げ物、天ぷら、ウナギで5~6時間かかるとされています。さらにバターは12時間とされ、バターを多く使ったグラタン料理や、一般に脂質の多い中華料理は消化に長い時間がかかることになります。寝ながらも消化中となると、そのカロリーは肝臓に蓄積されることとなって、将来の脂肪肝の原因となっていきます。
そのため、夕飯がやむを得ず遅い時間の場合は、できれば消化の早い食事を摂るようにしましょう。そして逆に会合後の夜中に、〆のこってりしたラーメンやアイスクリームなどは避けるようにしましょう。
狭い、硬い
今年度もすでに半分が過ぎて、今年の健診は済んだ方も多いのではないでしょうか。その健診では、コレステロール等の脂質の異常値を指摘されることがあります。
動脈硬化は、血液中に増えすぎたコレステロールが血管壁の内側に入り込むことで、血管壁の柔らかさが失われて、狭くなったり硬くなった状態をさします。動脈硬化は、加齢とともに誰にでもみられるものですが、特に脂質異常や糖尿病、高血圧、喫煙は、動脈硬化を促進してしまいます。脂質の中でも、HDL-コレステロール(善玉)は、余分なコレステロールを全身から回収して肝臓に戻すのに対して、LDL-コレステロール(悪玉)は全身に運ぶため、増えすぎると動脈硬化を促すことになります。また中性脂肪は、増えすぎるとLDLの小型化を促して、血管壁に侵入しやすくなるほか、血糖の上昇も促してきます。以前LDLとHDLの値は、2倍以下が望ましいとされていました。共に基準値以下としても、HDL値が下限値付近でLDLが基準上限付近で、比が2倍以上の場合は、やはり動脈硬化がみられてきます。HDLは,食事や薬で上げることは難しく、ウォーキング、ジョキング等の有酸素運動を行っていきましょう。LDLは有酸素運動を行うとともに、動物性脂肪やコレステロールが多い食事(肉の脂身、卵、バター、チーズ等)を控えて、食物繊維を多く含む野菜やキノコ、海藻、青魚、大豆製品を多くとるようにします。中性脂肪は、燃焼によって脂肪をエネルギーとして使うために、HDLと同じように有酸素運動をしていきます。また食べ過ぎ、飲みすぎを抑えて肥満を解消することで、中性脂肪は下がっていきます。
また現在の動脈硬化の進行具合は、ある程度推定することができます。エコーでの頸動脈への脂(プラーク)の付着程度、血圧を測るように手足に測定器をまくことでの動脈の硬さ、足の血管の狭窄の有無を知ることができます。管の入り口から水圧をかけると、硬い管は一気に出口から出てくるのに対して、柔らかい管は途中で伸縮するために出てくるのに時間がかかるためです。また途中で狭窄があれば、出口での圧力は下がることでしることができます。
硬くなってしまった血管を若い血管の状態に戻すことはできませんが、これ以上進行させないように、自分の血管状態に興味のある方は、かかりつけ医に相談してみましょう。
秋の予防接種
10月からはインフルエンザの予防接種が始まりますが、さらに今年は新型コロナワクチンの定期接種が加わります。今年春には全額助成の新型コロナワクチンの予防接種は終了し、10月からは自治体による定期接種となります。
予防接種には任意接種と定期接種があり、任意接種は各自の判断で行い、感染のリスクに対して免疫を得ようとするものです。インフルエンザや肺炎球菌ワクチン、海外旅行の渡航先で流行している感染症への予防接種などが該当します。
一方の定期接種は、国や自治体の予防接種スケジュールに基づいて行われる接種で、特定の感染症の予防を目的としています。定期接種はA型とB型に分けられ、A型では、乳児や小児に対して、麻疹、風疹、水痘、BCG、おたふくかぜ、日本脳炎、ポリオなどが当てはまります。B型は高齢の方に対して、感染時の重症化へのリスクを考慮して、特定の感染症の予防を目的としています。従来はインフルエンザと肺炎球菌があり、今回は新型コロナが加わりました。今年10月から来年1月末まで、接種時に65歳以上の方に対して接種費用には助成があり、今年仙台市では、季節性インフルエンザは1500円、新型コロナは3500円の自己負担分でできることとなりました。
季節性インフルエンザは、従来通り4価(A型2種、B型2種)のワクチンで接種が行われます。新型コロナは、以前オミクロン株派生のXBB株やBA4.5株に対するワクチンを行いましたが、現在は変異を繰り返して、ワクチンにはないKP.3株感染が多数を占めています。予防接種をしても感染しないわけではなく、また6ヵ月程度で免疫は低下するといわれています。そのため予防接種は、感染した後での重症化予防の意味になることから、特に高齢の方は普段から手洗い、換気等の感染予防を行い、万一感染してしまった時のことを考えて、予防接種はしておきましょう。また新型コロナワクチンの当初は、65歳未満での重症化しやすい基礎疾患のある方に対しても接種を勧められていました。ただ今回は特に推奨はされていませんが、心配の方は任意となりますがこの機会に接種しておきましょう。
たくさんの
最近、食品やサプリメントでは動脈硬化など生活習慣病の予防に役立つとして、ポリフェノールを多く含むという広告がみられます。フェノール成分を複数(ポリ)含むという意味から、ポリフェノールと言われます。
一方医療では、「ポリファーマシー」という考えがあります。ファーマシー(薬)が多い(ポリ)という意味で、「多剤併用」と訳されますが、そこには「┼有害な状況」も加わる、との考えも入っています。
心臓血圧や関節、腰痛、メンタル、認知症、胃腸等の不調の場合、それぞれの医療機関を受診して、病状にあった薬の処方を受けます。複数の病気があればそれぞれの薬が必要となりますが、薬の作用が重なってしまうと、副作用も出かねません。特に高齢の方ではあちらこちらの部位が不調となりやすく、そのため薬の種類が増えがちです。また薬を分解する肝臓や腎臓の働きも落ちてきており、統計では6種類以上の内服で、副作用も出やすく、また転倒も起こりやすくなるとされています。
病気を治すためにある医療機関で薬を出され、その薬の副作用に対して別の医療機関でそれを治す薬をさらに出される「処方の連鎖が実際に起きてきているとされています。それぞれの医療機関では、その症状を治すために薬を出しており、院外薬局の薬剤師や、処方した医師は薬の相互作用を極力注意しているものの、そのためにも薬手帳やマイナンバーカードはぜひ持参するようにしましょう。高齢の方での、降圧剤、メンタル薬、睡眠剤、認知症薬、胃薬、糖尿病薬、鎮痛剤等は、特にポリファーマシーになりやすいとされています。薬の増減の後で、体調で気になることが起こった時は、かかりつけ医か薬剤師に相談してみましょう。
薬が手元にたくさんあるという点から、自分の薬が合うからと人に譲るのは、厳に慎んでください。その方の体質、体調、内服している薬との相性はだれも知りません。何か副作用が起こった時の責任は、譲渡した方の責任となります。内服薬はもちろんのこと、貼付薬など外用薬も含めて、体調の悪い方が身近にいたら、自分の薬を譲るのではなく、早めの医療機関の受診を勧めましょう。
つって
梅雨があけて蒸し暑い夜には、熱中症や夏バテ予防のためにも、扇風機や冷房を使って、快適に寝たいものです。ただ、暑いので寝具から手足を出して寝ると、夜中に激しい痛みと共に足がつって目が覚めることがあります。
ふくらはぎや足などの筋肉が急につって激しい痛みを伴うこむら返り(有痛性けいれん)は、夏や冬に多いとされ、運動中や運動後の若い人にも見られますが、特に高齢の方に多いとされています。明らかな原因は不明ですが、寝ている時に起こりやすく、高齢の方に多いのは、歳と共に筋肉量が減ることで血液の循環量も落ちて、筋肉が必要とする血液、酸素が満たされないためにけいれんがおこるとされます。また足を冷やすことで血行不良となっても、つりやすくなります。夜中に寝具から足を出して寝ていて冷やしてしまい、激しくつった痛みで目を覚めるなどがあてはまります。また重い布団をかけて仰向けに寝ると、重さで足首を伸ばした状態となって足がつることがあり、さらに腰痛がある時に仰向けに寝ることで、腰に負担がかかって足がつることもあります。腰痛で仰向けが負担の場合は、横向きで休むか、ひどい痛みの場合は整形外科で相談してみましょう。
また暑い夜では就寝中の多量の発汗によって脱水がおこり、ミネラル分(ナトリウムやカリウム、カルシウムなど)も不足することで、足がつるとされています。普段からミネラルを多く含む魚介類や野菜などバランスの良い食事を摂った上で、就寝前に適量の飲水をして脱水の予防をしておきましょう。また普段から適度な運動や筋肉のストレッチをするようにしましょう。これらの脱水や、腰痛となって現れる脊椎の病気の他にも、原因として高コレステロール血症での内服薬による副作用、重い糖尿病や足の血管の病気による血行障害、肝硬変症や腎不全、妊娠中でもつることがあります。
もしつってしまった時は、ふくらはぎの筋肉をゆっくり伸ばす、湿布を貼ったり痛み止めを飲む、こむら返りのための漢方薬を飲むなどを行います。ただこの漢方薬は副作用も知られていることから、頻回につる時は、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。
今年の夏は
梅雨が明けると、今年も蒸し暑い夏がやってきます。特に昨年は、10月まで暑さが続いた思いがあります。最近は熱中症による緊急搬送が非常に多く、昨年の5月から9月では、救急搬送された人数としては平成20年以降2番目に多かったとのことでした。当初関東甲信越地方で始まった熱中症警戒アラートは、現在全国で発せられるようになっています。
熱中症は、体温をコントロールしている脳は平熱に設定しているのに、体温が異常に上昇して汗をかいて下げるなどの冷却がうまくいかない、異常状態に陥った状況です。そしてそれは体が暑さに慣れていない梅雨の合間の暑い日や、梅雨明け早々に多いとされています。熱中症による救急搬送は、高齢者が最も多く、次いで成人、少年、乳幼児の順になっています。また発生場所としては、家の中が最も多く、ついで路上や屋外等となっています。普段元気な方の、労働やスポーツ中での発症は、体の異常に気づきやすいことから軽症が多いとされますが、屋内での高齢の方の場合は、暑さを感じにくく、のどの渇きに気づかずに徐々に脱水状態に陥って、重症例が多いとされています。予防として室内では、温度計、湿度計を見やすい所に置いて時々チェックする、室温が28度、湿度は70%を超えないようにエアコンを積極的に使う、扇風機を使って室内の空気を循環させて、水分を定期的にとるようにしましょう。また家族の方は、高齢の方に積極的に声掛けするようにしましょう。
熱中症の初期症状には、めまいや立ちくらみ、気分不良、筋肉がつるなどがあります。体調不良で熱中症を疑ったら、早めに涼しい場所で冷えた経口補水液(OS-1Ⓡ)を飲むことが適切とされます。ただそれが塩辛く感じたり、また脱水予防のためであれば、市販のスポーツドリンクや、真水ではなくて、0.1~0.2%程度の食塩水(水1Lに食塩小さじ1杯1~2g程度と砂糖大さじ2~4杯20~40g程度)で水分補給をしましょう。また保冷剤などで首筋や脇の下、太ももも付け根を冷やしたり、涼しい風をあてて気化熱で冷やします。ただし意識がなかったり、意識があっても自分で飲水ができない状態の時は、速やかに救急車を依頼して、医療機関を受診しましょう。
歯の健康は体の健康
今年も6月4日から、「6(む)」「4(し)」にちなんで、歯と口の健康週間が始まりました。これは歯科疾患の予防と共に、早期発見、早期治療をすることで、歯の寿命を延ばし、体の健康にもつなげていこうというものです。
歯の病気でよく言われるのは、むし歯と歯周病ですが、特に歯周病は内科疾患との関係が知れられていて、その中でも糖尿病が強く上げられます。 糖尿病は、普段から高血糖が続く病気のために、細菌に対する抵抗力が低下していきます。重い糖尿病では、血行障害や神経障害で痛みを感じなくなり、そこに細菌感染が加わることで敗血症となって命に関わり、足の切断という事態も知られています。一方、口の中では歯周病菌が悪さをしていきます。歯周病菌が作り出す、歯の表面や隙間に付着したねばねばした物質(プラーク)は、しばらくすると歯磨きでは取れない固い塊(歯石)となります。その歯石の中でも歯周病菌が増殖し続けて、毒素を放出して歯周病を起こしていきます。そしてこの菌や、歯周病の炎症部位からサイトカインをいう化学物質が血液中に流れて、全身に影響を与えていきます。このサイトカインは、血糖を下げるインスリンの効果の邪魔をするために、血糖が上がって糖尿病の悪化を招きやすくなります。糖尿病が悪化すれば→免疫能が落ちて歯周病が悪化する→歯周病が悪化すれば血糖が上がる→さらに糖尿病が悪化する、の悪循環に陥ります。糖尿病があると歯周病の発症率は、健康な場合と比べて2倍以上高いとの報告があり、また歯周病の治療を受けると、1~2か月前の血糖の平均値(HbA1c)が0.4%ほど低下したとのデータも知られています。
さらに歯周病は、血管や免疫能に影響を及ぼすことから、糖尿病以外にも全身での脳梗塞、心臓病、慢性腎臓病、誤嚥性肺炎などとの関連も知られています。歯周病予防には、適切な歯磨きなどで、まずはプラークの発生を抑えること(プラークコントロール)が重要です。たかが歯、歯周病かもしれませんが、されど歯周病、侮りは禁物です。全身に影響する病気予防のためにも、歯科で定期的に歯石除去や歯周病健診を受けるようにしましょう。
食品でも
「健康食品」には、健康に良い成分で、できれば摂取していきたいとのイメージがあります。ただ昨今良かれと思って摂取していたサプリメントで健康被害が発生し、大変残念ながら不幸な事態が起こってしまいました。実際に「健康食品」という名前は、特に規制がないために、どのような食品にも使用ができます。そこで国は食品の中でも安全性や有効性等が一定の基準を満たした食品を「保健機能食品」として、さらにそれを「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に分けました。これらは報告したデータを国が審査して、許可するなどのハードルが高いために、その後平成27年に「機能性表示食品」という表示ができ、これは業者の責任で国に届けて販売するものです。
「特別保健用食品(トクホ)」は国が安全性、有効性を審査して、体に有益とのデータがあって、「おなかの調子を整える」等、健康維持、増進に役立つ、または適する旨が書かれています。「栄養機能食品」はビタミンや、亜鉛や鉄といったミネラルなど、特定の栄養素の補給を目的とした食品で、一日の摂取目安量や注意事項も表示した上で、国が決めた基準に沿っていれば、栄養成分の機能を表示することができます。それに対して「機能性表示食品」は、国の審査を得たものではなく、有効性、安全性を国に届けた上で、業者の責任で効能を表示して、健康維持、増進に役立つ等の旨が記されています。そのため万が一摂取で問題が起こった際は、業者が速やかに国に報告することになっています。しかし今回の健康被害は、この食品に該当していて、報告が遅れてしまった背景があるようです。またこれら以外では、下痢など特定の状態、疾病の際に有効であるデータがあって、国が認めた「OS-1Ⓡ」などの「特別用途食品」があります。一方、有効性のデータが確認されていない一般の食品でも、「栄養強化食品」、「健康補助食品」等の紛らわしい表示記載が可能となっています。あまりにも似た表示が多いために、自分がどのような食品(サプリメント)を摂っているのかは、注意が必要です。購入前にチェックしてみましょう。
また薬や「健康食品」を摂り始めて、すぐに発疹や健康被害がおこる場合と、数か月も経ってから発疹や体調不良、肝機能、腎機能障害に気づくことがあります。異変に気づいたら、まずは摂取をやめて、早急に医師や薬剤師に相談してみましょう。
腎臓のため
新年度になると、今年も住民健診や会社の定期健康診断が始まります。仙台市では、国民健康保険に加入している40~74歳までの方の特定健診が例年通り6月から、75歳以上や35歳~39歳の方の基礎健診が7月から始まります。この特定健診の目的はメタボ健診であり、動脈硬化による将来の腎不全、脳卒中、心筋梗塞といった血管疾患の予防を目的としています。
仙台市のデータでは、仙台市健診でのメタボ該当は約23%と、他の政令指定都市や全国の割合約20%を上回っています。また勤労世代の肥満の割合は男性で約30%、女性19%とされています。さらに1~2か月前の血糖の平均であるHbA1c(6.5%以上で糖尿病の疑い)6.5%以上の割合は、男性で約16%、女性で約8%となっています。仙台市での透析患者数は令和3年で約2550人と、近年ほぼ右肩上がりに増加してきており、そのためメタボが原因での将来の透析者数を減らすべく、病院の腎臓専門医との連携事業が始まっています。
動脈硬化、腎機能低下のため透析導入に至る予防策として、昨年までは太白区、若林区をモデル区として始まっていたのが、令和6年度から全市的に始まります。健診の結果で人工透析に至るリスクの高い方に対して、早期に腎臓専門医のいる病院に紹介して、予防への道筋をつけようとするものです。特定健診の採血には、腎機能を見るための項目(クレアチニン)があります。クレアチニンは、不要な成分が腎臓でろ過されないでどれだけ残っているかを見る項目です。加齢とともに低下していきますが、年齢の割には既に低下しすぎている場合、尿に蛋白、潜血がみられる時は、将来の腎機能低下が予想されてきます。その将来の腎機能低下による透析へのリスクが予想される場合は、腎臓専門医への紹介、受診が勧められます。
特定健診対象年齢の方の健診申し込みは不要ですが、75歳以上の方など基礎健診対象の方は自分での申し込みが必要です。仙台市政便り4月号か、市のホームページからぜひ申し込みをしましょう。また高血圧、糖尿病、高コレステロール等による治療中で、腎機能が気になる方は、ぜひかかりつけ医に相談してみましょう。
今シーズンでは
立春が過ぎて、今年もスギ花粉に悩まされる季節がやってきました。スギ花粉の飛散数は、前年のスギの雄花が作られる6~7月の気象が影響を与えるとされています。昨年は、暑さが10月まで続いた思いがありましたが、今年の仙台での飛散は2月下旬から始まり、昨年よりは少ないものの、例年よりはやや多いと予想されています。スギ花粉の飛散開始時期は、以前は3月上旬からが多かったのが、今回は早まってくるようです。毎年症状が出ている方は、早めに対応していきましょう。
スギ花粉症状がある有病率は、10年で10ポイントずつ増えているとされ、最近は50%近くの方が症状をもっているとされています。一方で新型コロナウイルスは、依然としてインフルエンザと共に流行していますが、花粉症では、発熱や息苦しさはなく、目や鼻が痒くなったり、それらによって感染症とは区別されます。
花粉症の治療には、まず抗ヒスタミン薬を内服しますが、飛散の始まる前から内服を始めた方が症状を抑え込めると、されています。これまでも悩まされた方は、早めに内服を始めましょう。さらに内服しても症状がある時には、点眼薬や点鼻薬を使うことになります。ただ内服薬には、眠気をおこすもの、気づかないうちに仕事の能率を落としてしまうものがありますから、内服の時は、まず医療機関に相談してみましょう。
花粉症の予防は、まずは体に花粉を近づけないことであり、毛織の上着は花粉が付着しやすいとされています。仙台ではまだ寒いために、毛織のコートを着ることが多いかもしれませんが、帰宅したらコートや髪から花粉を払い落としてから家に入りましょう。また飛散予報をみて花粉の飛散の多い日は出かけない、マスクや眼鏡をかけるようにします。スギの飛散時期は約2カ月、桜が散る頃までで、せいぜい4月いっぱいです。毎年スギ花粉でつらい思いをする時は、来シーズンの症状を抑え込む舌下免疫療法も始まっています。毎年つらい症状が出る方は、かかりつけ医師や薬剤師に相談してみましょう。
寒さで
立春を過ぎても、まだまだ寒くて春が待ち遠しくなります。寒さで血管は収縮することで、脳出血、くも膜下出血の多い時期となります。脳卒中のなかでも、脳梗塞は脱水による夏、血圧による冬と季節を問わずに起こりえますが、2割を占める脳出血は冬に多いとされています。
背景には脳血管に動脈硬化が起こっているところに、さらに血圧の大きな変動のために血管が破綻しておこります。脳出血では出血で血の塊ができた上に、頭蓋骨内の決まった容積の中でおこることから、本来の脳組織そのものを圧迫することになります。そのため意識がなくなったり、手足のまひや言語障害、認知機能の低下が現れます。またくも膜下出血では、激しい頭痛や意識障害が現れます。これらは早急に手術して血の塊を除去するなどの処置をすれば、後遺症も軽く済みますが、多くは半身不随や意識障害、認知症や寝たきりになったり、不幸な結果につながることが多いとされています。
脳出血やくも膜下出血の原因としては、血管が破れる高い血圧が最大の要因であり、他には動脈硬化を進める喫煙や大量の飲酒があげられています。また血圧が高くなる最大の要因は、食塩の摂りすぎです。日ごろの食事の中で、洋食は脂質が多いのに対して、麺のスープ、漬物、魚肉の練り製品といった和食、一般に濃い味付けの外食やコンビニ弁当では、食塩をとる量が増えがちです。薄味でとるようにし、食塩は1日6g以下と提唱とされていますが、普段どれくらいの塩分を摂取しているかは、尿から測定することができます。血圧が高めの方は、かかりつけ医に相談してみましょう。予防のための食事には、ナトリウムの排出を促す果物、野菜、大豆等の豆製品があります。意識してとるようにしましょう。また軽く汗を流して血流をよくするジョキング、ウォーキングなどの有酸素運動も効果的です。
最近の国の統計では、脳卒中(脳血管疾患)は、死亡原因の4位ですが、寝たきり状態で高介護となる原因としては、1位とされています。普段から脳卒中にならないように注意したいものです。発症後の治療は、時間との勝負です。腕が上がらない、顔がゆがむ、しゃべられない、周りからみて意識がおかしいといった症状の他に、これまで経験したことのないような激しい頭痛があった時は、速やかに脳の専門医療機関を受診しましょう。
今年の年末年始は
新型コロナ感染は5類となって、今年の年末年始は久しぶりに夜の飲食の機会も増えるかと思います。ただ遅くまで食事をすると、夜中や翌日には胃が重かったり、胸焼けを感じることがあります。
胸焼けは、みぞおちや胸骨の下縁付近が焼けるようなチクチクと痛む症状で、背中までも痛むこともあります。食道は酸に弱く、胃液が逆流すると傷害を受けやすくなります。短時間の逆流であれば、問題ありませんが、長時間であると炎症(逆流性食道炎)を起こしてきます。この病気は成人の10~20%はかかっているとされ、中高年、特に高齢の方に多いとされています。みぞおちや背中の痛みの他にも、寝ると口の中に酸っぱい水が上がってくる、のどの違和感、声のかすれ、心臓や肺に問題がないのに慢性の咳が続くことがあります。そのため声のかすれから耳鼻科を受診して、逆流性食道炎を指摘されることもあります。胃と食道の境には括約筋があって普通は胃液の逆流を抑えているものの、その括約機能が弱って胃の内容物が上がりやすくなったり、空腹時に胃酸分泌が増えすぎたところで、炎症がおこってきます。
逆流性食道炎の発生原因としては、
1.
消化に時間がかかって、胃酸分泌が増える脂肪分、タンパク質の摂りすぎ、アルコール、炭酸飲料の飲みすぎ
2.
腹圧が上昇する原因である、肥満、ベルトやコルセットで腹部を強く締めすぎる、食後にしゃがむことが多い、腰が曲がっている
3.
飲食後にすぐ寝る習慣
などが、あげられます。
予防として、食後すぐに横にならない(少なくとも2~3時間は上半身を起こしていて眠い時はリクライニング椅子を利用する)、普段から腹八分目の飲食をする、炭酸飲料やアルコール、グレープフルーツジュースなど酸性の強い飲み物を控える、揚げ物や脂っこい食事、海藻、きのこなど消化に時間のかかる食事は、特に就寝前は減らします。もし夕食前等空腹時に胸焼けが気になる時は、胃酸を薄めるために、酸を中和するアルカリ性食品(牛乳、ヨーグルトなど)がおすすめです。
ただ注意は、狭心症や食道がんなどの疾患でも、胸焼けの症状が出てくることがあります。症状が長く続く時は、一度はかかりつけ医に相談しましょう。
年末年始に
今年も年末が近づいてきました。昨年までとは違って、会合や飲酒の機会も増えるかと思われますが、節度ある適度な飲酒で楽しみたいものです。
適度の飲酒とは、依存症や内臓障害に至らない量であり、一日平均で純アルコール量20g程度とされています。純アルコール量は飲酒量(ml)?アルコール度数(%)?0.8(アルコール比重)から計算され、ビールでは500ml、日本酒1合、ワイン250ml、7%酎ハイ350ml1缶程度となります。ただし高齢者、女性、アルコールに弱い方は、さらに少ない量が推奨されています。過剰なアルコール摂取は、脳、心血管、肝臓など多岐にわたる臓器への障害が知られています。特に肝臓には負担がかかることから、一時的に過剰にとってしまった場合や、連日晩酌をしている場合は、飲酒をしない休肝日を週2日程度設けましょう。
そして連日の多量の飲酒が続けば肝臓に負荷がかかり、将来アルコールが原因の肝硬変症や肝臓がんへの移行が知られています。アルコールの分解には肝臓での分解酵素の働きが必要であり、日本人の4割はその酵素をあまり多く持っていない(それほど酒に強くない)、4%はほとんど持っていない(酒を飲むと具合が悪くなる、飲めない)とされています。そのためそれらの方は、過剰のアルコールによる肝疾患にはまずなりません。ただその分甘いものをとりすぎたり、運動不足があると、同じように肝臓に中性脂肪が蓄積されて、進行すると脂肪肝による肝機能障害が知られています。日本人の成人の20~30%には脂肪肝があるとされており、以前は減量、運動をしていればいいとされていました。ただ最近は飲酒が原因と同様に、肝硬変や肝臓がんに至ってしまう場合があることが知られてきました。その基礎には過度の肥満や糖尿病、高脂血症、メタボリックシンドロームがある場合とされています。今年夏には、特定健診、基礎健診といったメタボの健診がありましたが、肥満や糖尿病、肝機能障害を指摘された方は、かかりつけ医と相談の上で、ぜひ対処していきましょう。
食欲の秋には
最近は日没も早くなり、いよいよ秋らしくなってきました。秋は新米、果物、鍋料理などの食欲の秋であり、食材の香りや味を楽しむ味覚の秋でもあります。
最近の新型コロナウイルス感染では、感染力は強いものの、予防接種の効果もあって重症に至ることは減ってきました。ただ感染後に、さまざまな後遺症がみられています。その中でも、嗅覚障害や味覚障害が知られており、せっかくの食材でも香りや味がわからないために、食事が楽しめなくなってしまいます。
一方、新型コロナウイルスに感染しなくても、味覚が異常となることがあり、それは最近増加傾向にあるとされています。舌の表面には、味を感じるセンサーとなる味蕾があり、その情報が脳にうまく届かないと味覚障害となります。その原因としては、加齢によるもの、うつやストレスでのメンタルの不調、新型コロナや風邪の感染後、内服している薬剤の副作用が知られています。ただ味覚障害の原因の半数以上が、亜鉛不足によるとされます。亜鉛は全身の細胞内にあり、体の免疫システムや遺伝物質の合成、創傷治癒、乳幼児の成長、嗅覚、味覚に必要とされます。亜鉛不足は、偏った食事や、糖尿病や肝臓、腎臓など内臓の病気でもおこることがあり、味覚障害の他、慢性下痢、皮膚炎、食欲不振がみられてきます。国の日本食品標準成分表によると、亜鉛は、食材ではカキなどの貝類、豚レバー、牛肉の赤身、豆類などに多く含まれています。食べられる量100gあたりでみた亜鉛含有量は、精白米1.4mg、小麦やパンは1mg未満に対して、生カキ14mgしじみ2.3mg豚レバー6.9mg牛肩赤肉5.7mg大豆3.9mささげ4.9mg生ほや5.3mgなどと多く含まれています。それらの食材をいちどに大量に食べられるかは別として、味覚に不安のある方は普段から摂るように心がけましょう。また亜鉛の血中濃度は測定ができることから、症状があって不安な方はかかりつけ医に相談してみましょう。
7回目
新型コロナ感染は5類に変わって生活様式も緩和されてきましたが、感染者数は増加傾向にあります。その中で9月20日から7回目のワクチン接種が始まり、今回のワクチンは、XBB.1.5に対する1種類(1価)のワクチンとなります。今年春から9月19日までは同じオミクロン対応でもBA4/5の2価であり、異なったタイプのワクチンでした。現在、感染の主流はXBBに変化してきています。新型コロナウイルスは、以前のアルファ株、デルタ株等からオミクロン株に変異しており、そこからBA1、4/5に変異していった系統と、XBBに変異していった系統に分かれていきました。そのためBA4/5のワクチンをしても、XBBに対する免疫はそれほど上昇しないとされています。
今回のワクチンの目的も、重症化、入院予防となります。XBBタイプは、これまでのタイプよりも、さらに免疫防御をくぐり抜けやすく、感染力も強くなっています。9月からの接種対象は生後6か月以上のすべての方ですが、高齢者、基礎疾患があって重症化しやすい方は、特に接種が勧められています。来年春までに接種は1回の予定であり、今年度までが接種費用負担なしとなっています。次回8回目は来春以降となり、またワクチンでの免疫能は半年程度で低下することから、今年春に接種をした方は、年内での接種が望ましいかもしれません。また今回は、季節性インフルエンザの予防接種時期と重なっています。通常ワクチンは、新型コロナワクチン接種とは、少なくとも2週間はずらすことになっています。しかし季節性インフルエンザだけは、新型コロナワクチンと同日接種が可能となっています。ただ、それぞれ肩と肘の上付近への接種であり、副反応を考えれば少なくとも2~3日はずらした方が、現実的かもしれません。
今回も接種は、これまでに仙台市から送られてきた接種券を使って行います。市外からの転入の方や接種券の紛失などについては、仙台市ワクチン接種専用コールセンター(電話0120-39-5670)にお問い合わせください。
涼しくなったら
立秋が過ぎてもまだ暑いですが、真夏日は減ってなんとか過ごしやすくなってきました。5月から新型コロナが5類に移行したものの、戸外での運動がしにくかったこともあって、今年度の健診では、腹囲長が伸び、体重増になった方が多いようです。
メタボリック症候群の改善、内臓脂肪の減少を目指すためには、食事では揚げ物、肉の脂身、ケーキ等の脂質や、ジュース、果物、菓子、ご飯
もの等の炭水化物、カロリーとしての飲酒量を減らすこと、就寝直前には飲食しないことが重要となります。これらを実践したうえで、脂肪を燃
焼させるために運動をしていくことになりますが、有酸素運動(呼吸をしながらの運動)では、種類や強度の違いでの効果の差は認められていま
せん。ただ摂取したカロリーを消費するという目的であれば、ゆっくりとした散歩では、時間あたりの消費カロリーは当然少なく、目標とするカ
ロリーを消費するためには、運動する時間を長く要することになります。一方でもし短距離を高速で走るとすれば、時間当たりの消費カロリーは
伸びますが、長続きする運動ではありません。ウォーキングやジョキング、水泳、自転車でもエネルギー消費を高めるように実践することが重要
です。習慣として長期間に行って、苦痛に感じないレベルであれば、ややきついかなといった中程度の負荷を、一回20分程、週3回程度をめど
にかけることになります。普段から、2階、3階へはできるだけ階段で上る、近い距離は車を使わずにやや早歩きをするようにします。ただ心疾
患、血圧など何らかの病気で治療中の方は、かかりつけ医に相談してから行うようにしましょう。
腹囲を1cm減らすとすれば、体重約1㎏の減量が必要となります。急激な減量は難しいとしても、標準体重(身長╳身長╳22÷10000)を目指して、毎晩風呂上りに体重を量る習慣をつけるなどをやってみましょう。
夏では
梅雨が明ければ暑い夏がやってきます。冬には、寒さで血管が収縮することで脳出血やくも膜下出血が多いとされています。一方夏では、寒さ
で血圧が一気に上昇することはないものの、大量の汗をかくことで脱水になりやすく、逆に血圧が下がって、血液がどろどろになって詰まりやす
く(梗塞)なります。特に就寝中は水分を取れないことから、梅雨明けから8月、夜間から起床後2時間に脳梗塞が多いとされています
夏には、
1)脳の細い血管に動脈硬化がおこって詰まる。高血圧の人に多く、初めは症状が出にくいものの、多発してくると認知症のリスクが出てくるタ
イプ(ラクナ梗塞)。
2)脳の太い血管にコレステロールの塊が付いて、そこに血液が固まって血管を塞いでしまう。太い血管のために広範囲の脳が障害を受け、半身
不随や意識障害等の重い後遺症を残しやすいタイプ(アテローム血栓性脳梗塞)
が多いとされ、予防するには、脱水状態に水分を補う意味から、就寝前や起床時に水を飲むようにしましょう。また発病には加齢や生活習慣が関
わっています。現在特定健診、基礎健診を行っていますが、脳梗塞の危険因子として、喫煙、高血圧、糖尿病、脂質異常が上げられます。予防と
して、動脈硬化を抑えるために、禁煙し、食べすぎ、多量の飲酒を控え、寝不足・肥満を避けて、適度の運動を心がけるなど、生活習慣の改善が
大変重要です。
脳梗塞の発症は、「FAST」(早く)で表されます。F(Face)顔がゆがむ、A(Arm)両腕を前に伸ばしても片方の腕が下がってしまう、ねじ
れる、S(Speech)うまく話せないといった症状が突然現れます。その時はT(Time)時間との勝負です。発症後4時間半以内に治療が開始され
ると、大きな後遺症を残さずに済むことがあります。救急車を呼んで急いで脳の専門医療機関を受診してください。
今年度から
新型コロナウイルス感染は5類移行になって、生活状況もやや変わってきました。ただ新型コロナウイルスは消滅したわけでもなく、22-23年の
冬には、インフルエンザの流行もみられました。これらの感染では気道の粘膜細胞を強く傷害するために、その後で二次性の細菌性肺炎をおこし
やすくなります。その中でも、最も多いのが肺炎球菌によるものです。肺炎球菌は、高齢者の3~5%は健康時でも鼻やのどの奥にいるとされ、飛
沫を介して感染していきます。通常は抗生物質で治療しますが、効かない肺炎球菌が増えてきています。重篤になれば、肺炎や菌血症、髄膜炎を
起こして死亡原因となっていきます。現実に高齢者の方の年代別死亡原因の1位、2位はがんや脳心疾患ではなく、肺炎です。そのため免疫をつ
けておく目的で肺炎球菌の予防接種が始まり、平成26年10月1日からは定期接種として行われています。
現在インフルエンザワクチンは、A型、B型の4種類の株(4価)でできており、新型コロナワクチンのオミクロン株対応はBA4/5の2価ワクチン
です。一方肺炎球菌の株は、現在100種類程度あり、そのうちワクチンでは23種類対応(23価)で行われています。この23種類で成人の重症肺炎
球菌症の7割を占めるといわれています。23価ワクチン(PPV23、Ⓡニューモバックス)は、65歳以上で70歳、75歳、80歳…と5歳ごとに、これま
では公的助成を受けて接種が進められていました。ただ、この助成は今年度が最後で、来年度からは65歳の方だけに絞られる予定です。これまで
接種していない方で、65歳以上で今年度に5歳ごとの区切りの年齢になる方は、是非接種しておきましょう。
また高齢者の肺炎球菌ワクチンには、その後2014年に13価(PCV13)、2022年に15価(PCV15)ワクチンが出てきました。これらのワクチン
は、23価ワクチンと異なった機序での免疫効果があるとされ、23価ワクチンは次第に効果が低下していくのに対して、13(15)価ワクチンはしば
らく効果が続くとされています。さらに23価ワクチンと時期をずらして接種すると、免疫機能のさらなる増強(ブースター効果)が認められてい
ます。そのため呼吸器、感染症の専門学会では、23価ワクチンと13(15)価ワクチンで、時期をずらしての接種を勧めています。今年度助成のあ
る年齢の方は、年度内に23価ワクチンの接種を、そうでない方や、すでに接種済の方も心配であればかかりつけ医に相談してみましょう。
腎臓の能力
年度が替わって、職場や地域ではそろそろ健診が始まります。仙台市でも例年通り特定健診、基礎健診がそれぞれ6月、7月から始まります。
れらの健診は、将来のメタボリックシンドロームへの予防、高齢になっての筋力の衰えからくるフレイル(健康な状態と要介護状態の間で、身体
機能や認知機能が低下した状態)の予防を目的としています。
それらの項目には、将来の腎機能低下予防からクレアチニン、eGFR(推算糸球体ろ過量)、尿蛋白の項目があります。肝臓で作られたクレアチ
ンが、筋肉収縮の際にクレアチニンとなり、それが腎臓から排出されます。その排出されないで血液中にいくら残っているかを見ているのが、
「クレアチニン」値です。値が低いほど腎機能(排出能)は良いことになりますが、体格で筋肉量が多いほど、また急な運動すると高い傾向にな
ります。逆に長期にわたって臥床が続くような病気で筋肉量が落ちたり、悪性疾患で体力消耗が著しい際はクレアチニン値が低下して、腎機能そ
のものは良くなったように見えることがあります。
また「eGFR」は、腎臓での血液ろ過量(尿を作る能力)を、クレアチニン値、性別、年齢から標準の体型(筋肉量)で計算しています。健診で
は60ml/分以上を基準としていますが、当然体型の違い(大柄の筋肉質や小柄のやせ型など)では異なってきますし、年齢でも変わってきます
(若い人は100ml/分程度あり、高齢ほど低下していきます)。ただ若いうちから既に低い場合には、将来eGFRがさらに低下すると透析になりかね
ないために、注意が必要です。
項目での「尿蛋白」が陽性の場合は、現在腎臓に負担がかかっている、将来の腎機能低下に進む危険ともとられます。そのリスク因子として
は、健診の項目にある、動脈硬化を進める要因の肥満、高血圧、LDLコレステロール高値、高尿酸、高血糖、年齢が挙げられます。さらに喫煙、
塩分の取りすぎ、腎機能に負担をかける内服薬(鎮痛剤など)、腎炎の有無にも注意が必要です。
eGFRが思ったより低い、尿蛋白陽性で不安に思ったら、健診の結果説明の際にかかりつけ医にぜひ相談してみましょう。
6回目
今年5月には、ようやく新型コロナ感染は5類感染(全数把握ではなくインフルエンザ感染のように決められた医療機関での数の把握)に変わり
ますが、連休明けには6回目のワクチン接種が始まります。
今年度の新型コロナワクチン接種は、12歳以上すべての方に対して秋から冬(9~12月)に行います。ただワクチンでの免疫能は半年程度で低
下することが分かったため、重症化リスクが高いとされる方にはその前、春~夏(5月8日~8月)にもやっておこうというものです。春の対象
は前回のオミクロン株対応ワクチン接種から3か月以上経って、初回接種(1・2回目)は終わっている方の内、65歳以上の方と、12~64歳で
基礎疾患のある方となります。基礎疾患としては当初のワクチン接種での対象と同じで、①気管支喘息、肺気腫などの呼吸器疾患、②高血圧も含
む心筋梗塞、狭心症などの心臓疾患、③人工透析中などの慢性腎臓病、④肝硬変などの慢性肝臓病、⑤糖尿病治療中、⑥鉄欠乏性貧血を除く血液
疾患、⑦免疫機能が低下する疾患、⑧抗ガン剤、免疫抑制剤での治療中、⑨睡眠時無呼吸症候群、⑩BMI(体重÷身長÷身長÷10000)が30以上の
肥満などが挙げられています。そのためこの中には、痛風などの高尿酸値、高コレステロール血症、胃炎や逆流性食道炎などは含まれていませ
ん。今年秋以降に使われるワクチンの種類はまだ決まっていませんが、春に使われるワクチンは主に昨年度と同じオミクロン対応となります。そ
のため接種後の副反応としては、前回とほぼ同様と考えられます。
ただ接種直後の急激な体調変化、アナフィラキシーショックについては今回も絶対ないとはいえません。前回までと異なるメーカーのワクチン
接種もあり得ることから、今回も接種から15~30分は体調の変化に注意が必要です。また接種はこれまでと同様、自治体から送られてくる接種券
を使って行います。市外からの引っ越しや接種券の紛失などについては、仙台市ワクチン接種専用コールセンター(電話0120-39-5670)や仙台
市ホームページ(接種券発行をご希望の方へ)にお問い合わせください。
4月から
4月からは、新年度の検診がまた始まります。
胃がん検診は、従来はバリウムを使ったX線透視での検診のみでしたが、2016年から、内視鏡検診も選べるようになりました。胃がんの原因と
して、ヘリコバクターピロリ感染が知られていますが、若い方の感染が減っています。ピロリ菌の感染率は50歳以上で40~60%なのが、10~20
歳台では10%程度と、欧米並みとなっていて、胃がんの発症も減っています。理由として、戦前戦後に井戸水などの生水を飲むことで感染して、
さらに親から子に口移しで食べさせて感染していたのが、生活様式の変化でそれらが減ったことが挙げられています。
仙台市の胃がん検診でも、現在は内視鏡検診とバリウムでのX線検診を選べるようになっています。ただバリウムでの検診対象が、年度末時点
で35歳以上の方であるのに対して、内視鏡検査は50歳以上となっています。また受診間隔がX線検診が毎年であるのに対して、内視鏡検診では2
年に一回となっています。そのため50歳以上の方で令和4年度に内視鏡検診を受ければ、5年度は検診は受けられない、4年度にX線検診を受けた
方は、5年度には内視鏡でもX線検診でもどちらか受けられることになります。
内視鏡検診の場合は、写真は検診直後と、宮城県対がん協会での2重チェックで診断され、最終報告は仙台市から届くために、結果がわかるのは
1~2ヶ月後となります。また胃がんを見つけるための検診ですから、基本的に検査は、写真を撮って診断することであり、検査結果から当日に
薬の処方や、ピロリ菌検査を行うことはありません。検査では喉の麻酔は行いますが、検査が心配、怖いとの理由での鎮静剤は使えません。また
胃がんの治療後や、胃潰瘍での治療中の方は、これまでの写真と比較しながらの検査が重要であり、検診での内視鏡検査はお勧めできません。か
かりつけの医療機関での内視鏡検査を受けましょう。
胃がん検診の申し込みは、4月初めの市政便りに載っています。これまで胃の検査をされたことのない方は、ぜひ一度は検査しておきましょう
今年も
立春が過ぎて、新型コロナ感染第8波の感染者数はやや減少傾向にありますが、まだ収束には至っていない状況です。今年もまたスギ花粉に悩ま
される季節がやってきました。2019年の全国調査では、国民のほぼ3人に1人がスギ花粉症と推定されています。また昨年の6~8月の最高気温、日
射量、これらと前年との比較から分析されると、昨年スギ花粉の飛散量は例年より少なかったものの、今年仙台では例年よりも逆に多いと予想され
ています。飛散の開始時期は2月下旬からですが、症状の出る方は昨年よりは強く出るかもしれません。昨年でさえ症状が出ていた方は、早めに対
応していきましょう。今年はインフルエンザの流行もみられ、さらに新型コロナの感染流行が重なっています。ただ花粉症では、目の痒みを伴うこ
とが多く、のどの痒みはあっても、のどのひどい痛みや高熱は出ないことから、体温の変化や症状の違いには注意していきましょう。
スギ花粉症の予防は、花粉を近づけないことであり、飛散の多い日は外出しない、マスクや眼鏡をかける、帰宅したら髪や上着から花粉を払い落
としてから家に入ることが基本です。新型コロナ感染予防でもマスクをつけているものの、マスクをすることで、マスクをしない場合よりも7割の
花粉を減らせるとの結果がでています。また普段は裸眼やコンタクトレンズをしていても、花粉飛散時は眼鏡にするだけで、目に入る花粉は4割減
らせるとされています。仙台でのスギ花粉の飛散時期には、まだ雪が降ったりして寒いですが、外出の際ウール製の上着、セーターは、化学繊維や
木綿の上着よりも花粉が格段に付着しやすいとされています。外出時には着るのを避けるか、家に入る前に入念に落としてから入るようにしましょ
う。
花粉症の治療には、まず抗ヒスタミン薬を飲みます。内服は、飛散の始まる前の1~2月から始めた方が症状を抑え込めるとされています。抗ヒス
タミン薬は、現在は眠気の起こりにくい第二世代の製品が主流です。ただその第二世代でも眠気を引き起こすもの、自動車運転、危険作業を避ける
必要がある薬があります。そのような薬は、内服してもなんら変わらないと思っていても、単に自分が気づかないだけで、試験をすると集中力、作
業効率が明らかに低下するという現象がみられています。
スギ花粉症の季節は約2ヵ月、処方された薬で眠気やだるさを感じる、不調の時は、かかりつけ医師や薬剤師に相談して辛い季節を安全に乗り切
りましょう。
温度差で
年が明けて、大寒から立春へと暦が移っても寒さはいよいよ厳しくなり、春が待ち遠しくなります。新型コロナウイルス感染予防での外出自粛は
緩和されてきましたが、寒い夜には入浴で温まるのが楽しみです。
ただ入浴中の事故は冬に多いとされ、年間の80%が11月から4月の間に発生しているとされています。入浴の前後には血圧が大幅に変動します。
冬に暖房の効いた温かい部屋では、血管は拡張していて血圧はあまり変化していません。ましてや飲酒中には顔が赤くなるように、血管が拡張して
血圧は下がっています。ただその後でトイレや入浴のために室外に出ると、寒さで血管は収縮して血圧は上がることになります。浴室とトイレは家
の北側にあることが多くて、比較的寒く脱衣中に血圧は急に上がります。その後お湯に入ると血管は広がって今度血圧は急激に下がり、浴室から出
ると血圧はまた上がるといった変動がおこります。その血圧の変動は心臓に負担をかけて(ヒートショック)、心筋梗塞や脳梗塞、脳卒中につなが
りかねません。特に高血圧や糖尿病、脂質異常、肥満、心臓病等の持病のある方、高齢の方は注意です。高齢になると血圧の変動が生じやすくな
り、体温を維持する機能も低下することから、ヒートショックの受けやすいと考えられています。65歳以上の方は特に注意が必要です。高齢者の浴
槽内での不慮の溺死、溺水は年齢と共に増加していきます。またトイレでも同じことが起こります。寒い思いをしながらトイレに入って便秘でりき
むと、温かい部屋での血圧は大きく変動して、失神や脳卒中に至ることがあります。
予防としては、食後すぐの入浴、飲酒後アルコールが抜けていない状態での入浴は控える、居間だけではなくて、脱衣室、トイレも暖める、浴室
も暖房をつけるか、もしくは給湯時に湯舟の蓋をあけておいて湯気を使って暖めておきましょう。入浴は41度以下のぬるめの湯に入り、湯舟につか
るのは10分程度として、熱めの湯、長湯を避ける、高血圧や心臓病等のある方は肩まで湯に入らずに、胸付近でとどめる、深夜に一人で入浴するこ
とを避けて、周りの方も声を掛け合うようにします。また便秘気味の方はりきまないでも済むように、便を緩くする薬を普段から内服するようにし
ましょう。これらに注意して、入浴中やトイレでの不慮の事故は、未然に防げるようにしたいものです。
寒さで
新型コロナウイルス感染も第8波となって、なかなか収束の兆しが見えません。
寒さはこれからが本番で、年明けにはさらに積雪での雪かきや、戸外での活動が増えていきます。また屋内でも、トイレや脱衣場はますます冷え
て、体には負担がかかってきます。寒い場所では体温が奪われないように、体表の血管は収縮します。一方雪かきや、登り坂、長い距離の歩行など
で体に負担がかかる時は、心臓も含めて、筋肉は血液中の酸素の要求量が増大します。その時、動脈硬化が進んでいて十分な酸素を供給できない時
には、胸の痛みや足のしびれや痛みが起こってきます。特に心臓の筋肉(心筋)は手足の筋肉と違って休めないために、狭心症の痛みとして起こっ
てきます。休息で手足の筋肉の酸素需要が減ることで、心筋への酸素供給が追い付いて症状が消えればいいですが、体にとっては将来心筋梗塞など
危険な状態に陥る前段階のサインです。胸が締め付けられる(絞扼感)、押し付けられるような圧迫感、焼けるような灼熱感と表現されます。場所
も心臓のある前胸部だけではなく、首筋や左肩、みぞおち、歯ぐきにまで拡がることがあります。さらにみぞおちに痛みが起こることもあり、胃痛
と思ったら狭心症だったということもあります。
この活動時(労作時)狭心症の原因は心臓血管の動脈硬化であり、そのリスクは健診で調べています。三大危険因子は喫煙、LDLコレステロール高
値、高血圧とされ、他にも高血糖や高尿酸、肥満等のメタボリックシンドローム、年齢が挙げられます。生活習慣では動物性脂肪(卵黄やロース肉
等)に多く含まれる飽和脂肪酸(ナッツやチョコレート、バター、ショートニング等にも多い)の取りすぎ、塩分の取りすぎ、アルコールの取りす
ぎ、運動不足、肥満、ストレスが狭心症のリスクを高めるとされています。年末年始には、特に運動不足や飲食の偏りが起きやすくなります。ぜひ
注意していきましょう。
また明け方の就寝中や安静時でも、同じような症状が現れることもあります。症状が頻回に続く時や、長時間になってきた時は早めにかかりつけ
医に相談しましょう。
年末年始には
クリスマスから年末年始は、ごちそうに舌鼓をうつ時期でもあります。基本の味覚には、甘味、酸味、塩味、苦味、うま味の5つが知られていま
す。このうち塩味は料理に欠かせないものですが、食塩(塩化ナトリウム)の過剰摂取は高血圧や心臓疾患、脳血管障害、腎機能の低下の原因等と
して挙げられています。
日本人の食塩摂取量は、かつて2000年初め頃は男性で一日12g程度、女性で11g程度でした。その後漸減してきましたが、最近でも男性で11g程
度、女性で9.3g程度とされています。食塩を過剰にとった場合、血液中のナトリウム濃度が上がり、体はそれを薄めるために、水分をため込んで濃
度を下げようとします。そのため血管内の血液の体積が増して、血圧が上がっていきます。また腎臓ではナトリウムを排出しようと過度に働き、ま
た高い血圧が腎臓の血管に直接来ることから、腎機能が疲弊しやすくなります。そのため国は、一日の食塩摂取量を男性で7.5g未満、女性で6.5g
未満にするように提唱しています。また日本の高血圧の専門医学会ではさらに踏み込んで一日6g未満へ、世界保健機関(WHO)は5g未満を提唱
しています。
この摂取量を目指すためには、普段から薄味に慣れる、食材の食塩含有量に注意することが必要です。醤油でも薄口と濃口では、見た目と違って
食塩量は薄口の方が多いとされています。塩分が気になる時は減塩醤油を使いましょう。また麺類の食事ではスープは残す、すべて飲まない、刺身
や寿司ではつける醤油を減らす、上からかけない、漬物、佃煮、塩辛は少量にする、今からの季節はおでんが美味しいですが、ちくわ等の練り製品
にはかなりの食塩が入っています。購入の際は、外袋の成分表示での食塩量を見てみましょう。
食塩摂取を減らすためには、塩味の代わりに酢などの酸味や香辛料を利用する方法もあります。またナトリウムと同時にカリウムを摂取すると、
カリウムがナトリウムの排出を助ける作用があります。カリウムは野菜や果物に多く含まれています。ただ果物には甘味(糖)もあることから、摂
りすぎではカロリーも過剰になってしまいます。注意しながら摂っていくようにしましょう。
また普段どれだけ自分が食塩を取っているかは、測定することができます。気になる時は、かかりつけ医に相談してみましょう。
2価ワクチン
今年も季節性インフルエンザワクチンの季節が始まりましたが、新型コロナウイルスワクチン接種では、2価のワクチンが始まりました。インフ
ルエンザワクチンは以前から、A型2種とB型2種の4種類のインフルエンザウイルスに対応したワクチン(4価)であり、新型コロナワクチンでは、
これまで接種してきた従来(起源株)型とオミクロン株BA.1(BA.5)対応型を混合した2種(2価)ワクチンとなりました。今回のワクチンには複数
のウイルス株が含まれていることから、さまざまな型のコロナウイルス株に効果があるものと期待されており、このワクチン接種は一回のみとなり
ます。またこの2価ワクチンは、ワクチン接種3回目以降の追加免疫のみに使われ、初回免疫(1,2回目)には使われません。10月中旬からは、初
回免疫(1,2回目)の接種が終了して、5か月経った方全員が対象となっています(ただ接種の間隔、5か月は今後短縮される予定となっていま
す)。
またこれまでに新型コロナに感染した方でも、感染後3か月空ければ、ワクチン接種を勧められています(例:前回ワクチン接種してから3か月
目に感染した場合は、それから3か月後、通しでは6か月後以降に接種)。それは、一度感染しても再感染があること、感染で獲得する免疫よりも
ワクチンでの方が抗体価が高くなること、さまざまな変異株に対する抗体の産生もみられるとの報告があるからです。なお2価ワクチンの副反応に
ついては、これまでの1価のワクチンと同様で、注射部位の痛み、だるさ、頭痛、筋肉関節痛、発熱等が報告されています。やはり接種翌日には、
休養を取りやすい環境を考えておいた方がいいかもしれません。
2価の新型コロナワクチンは、既に外国では始まっていましたが、長期間でみた安全性のデータは1価同様に揃っていません。接種をするかどう
かは結局自分で決めることになります。また接種の今後の具体的な日程や予約については、仙台市ワクチン接種専用コールセンター(電話0120-39-
5670)へお問い合わせください。